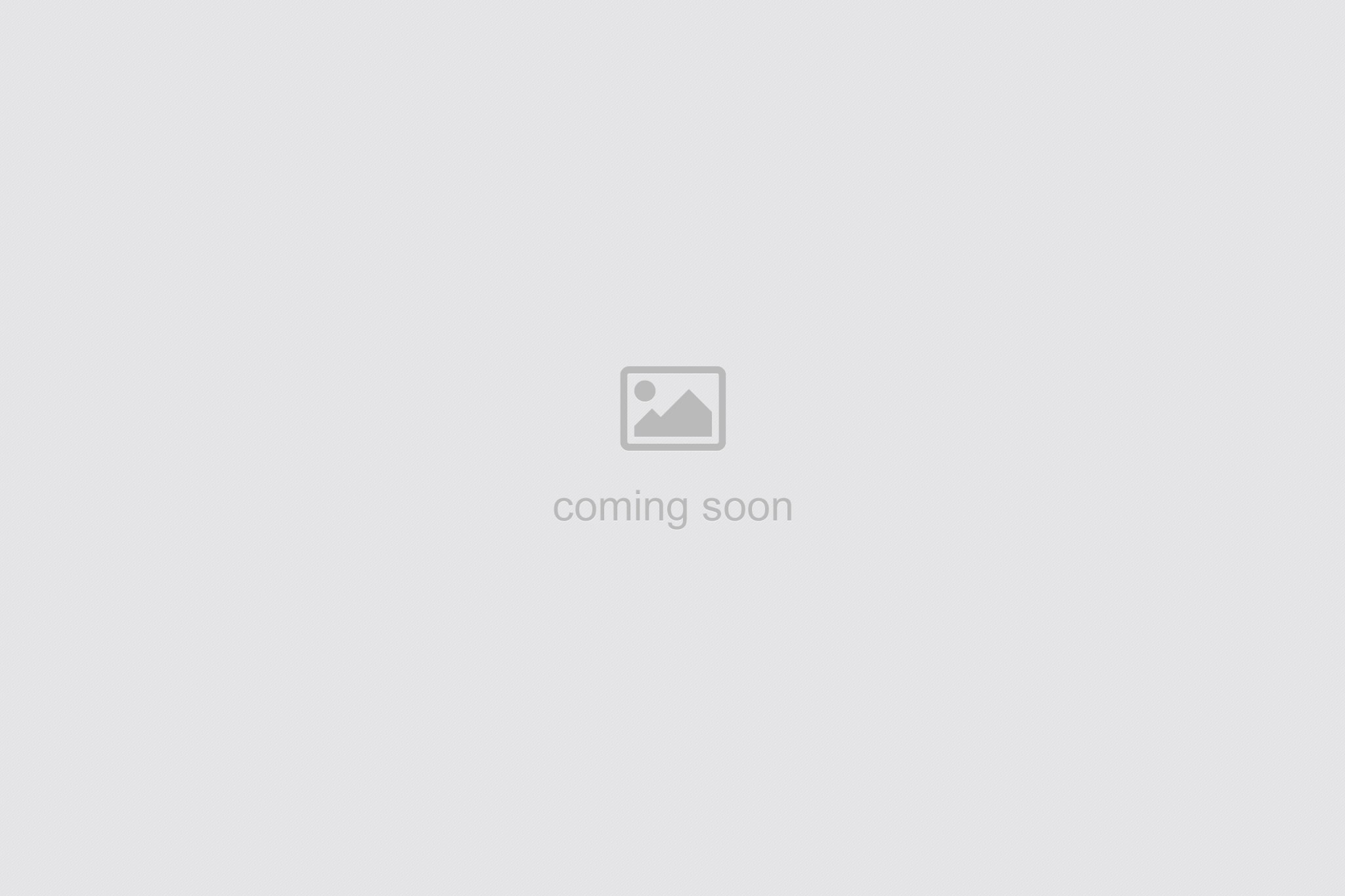活動報告:2006年
第16回夏季研究集会:シンポジウム「PISAショックを考える パートI」
2006-08-19
コーディネーター:
福田誠治(都留文科大学・運営委員)
パネラー:
末藤美津子(明治学院大学)
池田賢市(中央大学・運営委員)
嶺井正也(専修大学・代表)
(1)国際学力調査の受けとめ方
国際学力調査が質的に転換するのは、1990年代である。グローバリズムの時代に、教育行政が今や一国の内政にとどまらなくなったということである。
経済成長と学力とは深く結びつけられ、とりわけ教育の成果が技術革新を生むと見なされている。したがって、とくに理数系の学力を向上させるため、統制的・計画的な教育政策がとられることになった。このような道を選んだのは、日本やイギリス、アメリカなどである。ところが、ヨーロッパの学力向上策は、 OECDのPISAに見られるように創造性、批判的思考、自己信頼を大切にするもの注目される。また、その背景には、国境を越える学力観を作り出しつつあるDeSeCoの活動がある。
(2)イタリアの事例
PISA、 TIMSSともにイタリアの結果は芳しくない。これを受けて、イタリアでは、学力の南北間格差が議論に上がっている。北部だけをとれば、国際的な上位に相当するからである。したがって、南北間格差を生む経済格差の問題、後期中等教育の学校タイプの学力差などが改めて問題視されつつある。恐らく、経済資本が文化資本を媒介して作用するという論理が貫徹しているのであろう。したがって、ふさわしい文化活動が確保されるような社会的なバックアップが必要となるということになる。
(3)日本の事例
日本では、低学力批判、脱「ゆとり教育」という学習指導要領改訂という舞台装置ができあがっていたところに、国際学力調査の結果が報道されたので、学力の質の分析と適切な対策を論議するようには進まなかった。読解力向上にむけて文科省の動きが目立ったが、読書指導に傾いていた。その後、対策は「国語」だけでなく各教科、総合的な学習の時間など学校の教育活動全体で身につけていくべきものという変化が見られるが、学びの質を変更するほどの政策はない。むしろ、「PISA・TIMSS対応ワーキンググループ」の分析結果が政策に十分生かされていない。
(4)フランスの事例
フランスでは、PISAの結果はほぼ無視された。授業時間を増やせという動きもない。週5日制は守られており、中には週4日制という地域もある。また、7週の授業期間と2週の長期休業というサイクルも作り出されている。義務教育段階にあたる共通基礎では、学力の低い学校や地域により多くの援助を行い、「底上げ」を行っている。さらに、学力の成果について、学校や教員を制裁するような措置もない。むしろフランスの教育問題は、別のところにある。政治的には「共生」を唱えながら、『教育法典』では、「国家およびその歴史の学習を義務的に含む公民教育」と明記されており、移民問題の解決は容易でない。
福田誠治(都留文科大学・運営委員)
パネラー:
末藤美津子(明治学院大学)
池田賢市(中央大学・運営委員)
嶺井正也(専修大学・代表)
(1)国際学力調査の受けとめ方
国際学力調査が質的に転換するのは、1990年代である。グローバリズムの時代に、教育行政が今や一国の内政にとどまらなくなったということである。
経済成長と学力とは深く結びつけられ、とりわけ教育の成果が技術革新を生むと見なされている。したがって、とくに理数系の学力を向上させるため、統制的・計画的な教育政策がとられることになった。このような道を選んだのは、日本やイギリス、アメリカなどである。ところが、ヨーロッパの学力向上策は、 OECDのPISAに見られるように創造性、批判的思考、自己信頼を大切にするもの注目される。また、その背景には、国境を越える学力観を作り出しつつあるDeSeCoの活動がある。
(2)イタリアの事例
PISA、 TIMSSともにイタリアの結果は芳しくない。これを受けて、イタリアでは、学力の南北間格差が議論に上がっている。北部だけをとれば、国際的な上位に相当するからである。したがって、南北間格差を生む経済格差の問題、後期中等教育の学校タイプの学力差などが改めて問題視されつつある。恐らく、経済資本が文化資本を媒介して作用するという論理が貫徹しているのであろう。したがって、ふさわしい文化活動が確保されるような社会的なバックアップが必要となるということになる。
(3)日本の事例
日本では、低学力批判、脱「ゆとり教育」という学習指導要領改訂という舞台装置ができあがっていたところに、国際学力調査の結果が報道されたので、学力の質の分析と適切な対策を論議するようには進まなかった。読解力向上にむけて文科省の動きが目立ったが、読書指導に傾いていた。その後、対策は「国語」だけでなく各教科、総合的な学習の時間など学校の教育活動全体で身につけていくべきものという変化が見られるが、学びの質を変更するほどの政策はない。むしろ、「PISA・TIMSS対応ワーキンググループ」の分析結果が政策に十分生かされていない。
(4)フランスの事例
フランスでは、PISAの結果はほぼ無視された。授業時間を増やせという動きもない。週5日制は守られており、中には週4日制という地域もある。また、7週の授業期間と2週の長期休業というサイクルも作り出されている。義務教育段階にあたる共通基礎では、学力の低い学校や地域により多くの援助を行い、「底上げ」を行っている。さらに、学力の成果について、学校や教員を制裁するような措置もない。むしろフランスの教育問題は、別のところにある。政治的には「共生」を唱えながら、『教育法典』では、「国家およびその歴史の学習を義務的に含む公民教育」と明記されており、移民問題の解決は容易でない。