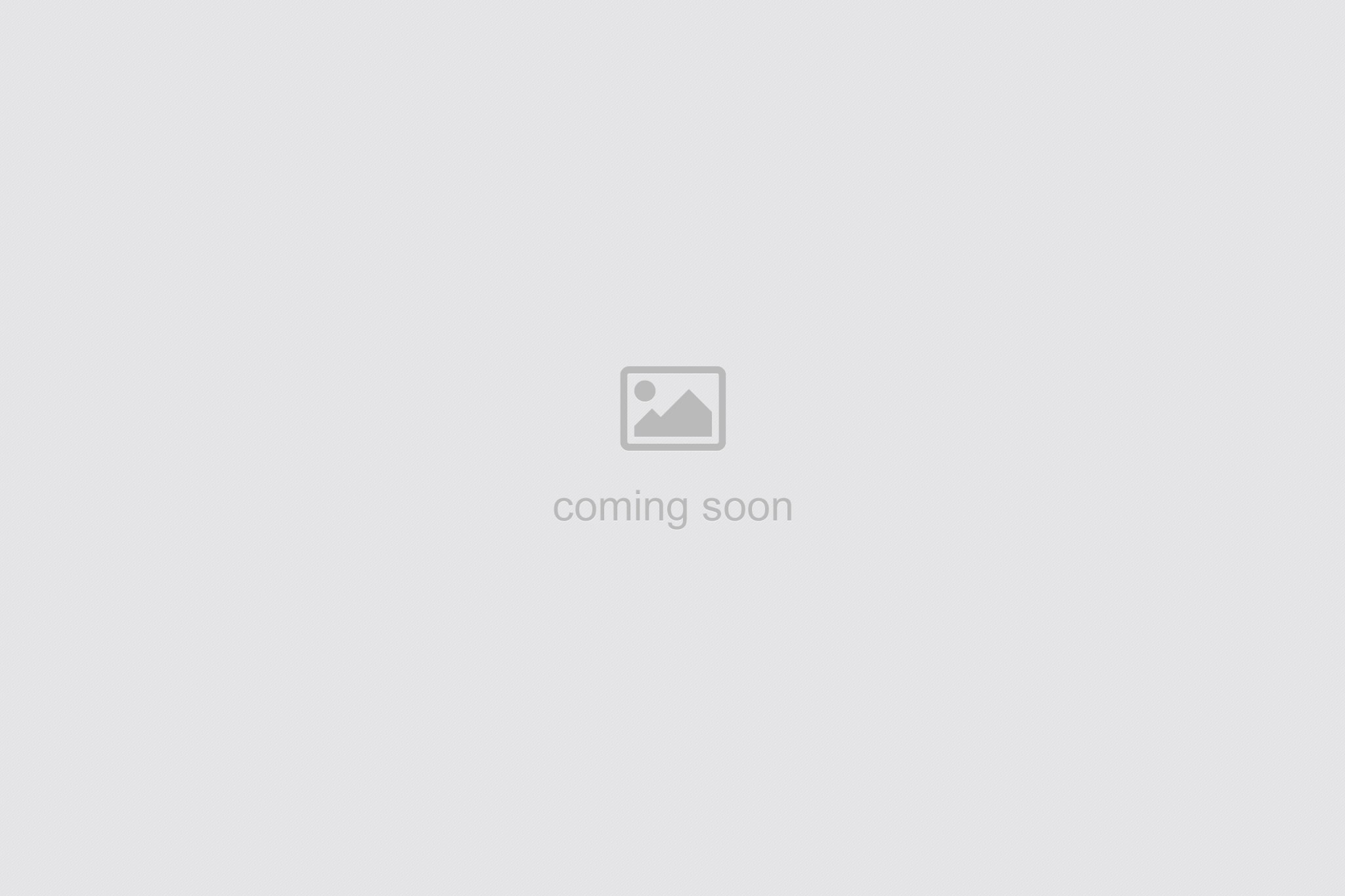活動報告:2007年
冬季研究集会シンポジウム「PISA2006を読み解く」
2007-12-09
12月9日日本教育会館で、参議院選挙のため冬季へと変更になった2007年度研究集会が開催された。その第2部として、「PISA2006を読み解く」を開催した。
教育総研としては、OECDのPISAが先進諸国を中心としながらも世界の公教育に大きな影響を及ぼすと考え、PISA2000の結果公表以来、これに注目し、フォローしてきた。
2003年3月にはフィンランド調査(他に、イタリアとスペインを訪問したので、PISAだけに焦点を合わせたものではない)、2005年3月には韓国とフィンランドの調査、さらに2006年8~9月にはデンマーク調査を行った。あわせて、この3年の間にEIとTUACの合同会議に参加し、各国の教職員組合代表から各国の情報を得、意見交換を行ってきた。
さらに、2006年には、夏季研と教育総研創立15周年記念シンポで「PISAショック」をとりあげた。
こうした調査研究の上に、今回のシンポを企画したのである。当日配布された資料は、各国政府や関係者の反応に関する資料が含まれており、非常に濃い内容になっている。
桜井智恵子さん(大阪大谷大学)をコーディネーターとして、シンポは福田誠治さん(教育総研運営委員・都留文科大学)、池田賢市さん(教育総研運営委員・中央大学)、広瀬義徳さん(松本短期大学)で行われ、会場との意見交換もなされた。
福田さんは12月4日に世界同時に(とはいっても既に政府レベルでは早くにデータが送られていたし、スペインではすっぱ抜きがあった)公表されたデータだけでなく、この間精力的に収集したデータや資料をもとに、①底上げが学力向上の定石(フィンランド、香港、カナダを見よ)、②テスト競争では学力は身につかない(イングランド、アメリカを見よ)、③日本の結果をみると、公式など結論を指示された設問に応用することはできるが、身の回りの具体的な事柄に科学的思考を応用することはどちらかといえば苦手、④日本の子どもたちは「科学への興味・関心や科学の楽しさを感じている」生徒の割合は低く、「観察・実験などを重視した理科の授業を受けていると認識している」生徒の割合も低い。これは自ら意欲的に学んでいないことを示している、⑤日本の科学の学力格差は数学に比べると学校間格差が小さい、一方、フィアランドはほぼゼロである、⑥PISAが定義する学力は、日本人がこれまで考えてきた、知識の量や、技能の正確さ・スピードを測るものではなくそれらを活用するプロセスを測るものである、だから、結論を与える授業ではだめで、身の回りから問いを発し、原理・原則に戻って考えるというような議論の中から考える授業が求められている、と報告した。
池田さんは、フランスの国民教育省のコメントやル・モンド紙の特集から、これまで2回のPISA結果とは違うフランスのPISA2006に対する反応を紹介した。過去2回とはちがい、少しはPISA結果に動揺している様子がある。それは「前回のPISAの結果はドイツ、スイス、日本にショックを与えたが、今回はフランスの番かもしれない」とか「フランスでは、PISAはそれほど深刻には受け取られていなかったが、この2006年調査によって事態は変わる可能性はある」、といった反応があるからだ。また、ル・モンド紙が「15歳の生徒に科学を好きにさせることは可能である。すべての小学校で、好奇心旺盛なその時期に、自ら作業をするようなスタイルの授業の実施が必要である」といった教育の方法にまで言及している、という興味深い報告もなされた。
広瀬さんは、前回と同じように今回もマスコミが、日本のランクが落ちたことを強調しており、日本は「あおられる学力不安社会」になっているとし、事実の冷静な認識と分析のためには①15位以内に順位を得た国のなかで、人口1億を超える大きな国は日本のみである、②学力パフォーマンスを分析する上で、少なくとも学習指導要領といったカリキュラム政策要因のみならず、学校組織要因(教員定数、学級編制など)、家族的背景要因、社会経済的要因、大衆消費文化的要因が指標として設定されなければならない、③社会経済的状況(格差社会)自体が抜本的に是正されなければならない、ことを指摘。最後に、学力以外に、人権保障度、文化的アイデンティティ保障度が調査されないのはなぜか、PISA学力とグローバル経済におけるエリート育成の親和性について分析する必要があるのではないか、など基本的な問題点にも触れた。
これを受けたフロアーとの議論においては、PISAをどう評価し位置づけるのか、コンピテンシーとリテラシーの関係、今回のマスコミ報道の評価、ユネスコの学習論との異同などが論点となったが、時間の関係で詰めるまでにはいたらなかった。
最後に、桜井さんがPISAの枠内で議論するだけでなく、一歩外に出てみることが必要でないか、日本の子どもたちが「意欲」では最下位に近いにもかかわらず、「成績」では上位をとっているというギャップも子どもを痛める問題ではないのか、などとコメントした。
教育総研としては、OECDのPISAが先進諸国を中心としながらも世界の公教育に大きな影響を及ぼすと考え、PISA2000の結果公表以来、これに注目し、フォローしてきた。
2003年3月にはフィンランド調査(他に、イタリアとスペインを訪問したので、PISAだけに焦点を合わせたものではない)、2005年3月には韓国とフィンランドの調査、さらに2006年8~9月にはデンマーク調査を行った。あわせて、この3年の間にEIとTUACの合同会議に参加し、各国の教職員組合代表から各国の情報を得、意見交換を行ってきた。
さらに、2006年には、夏季研と教育総研創立15周年記念シンポで「PISAショック」をとりあげた。
こうした調査研究の上に、今回のシンポを企画したのである。当日配布された資料は、各国政府や関係者の反応に関する資料が含まれており、非常に濃い内容になっている。
桜井智恵子さん(大阪大谷大学)をコーディネーターとして、シンポは福田誠治さん(教育総研運営委員・都留文科大学)、池田賢市さん(教育総研運営委員・中央大学)、広瀬義徳さん(松本短期大学)で行われ、会場との意見交換もなされた。
福田さんは12月4日に世界同時に(とはいっても既に政府レベルでは早くにデータが送られていたし、スペインではすっぱ抜きがあった)公表されたデータだけでなく、この間精力的に収集したデータや資料をもとに、①底上げが学力向上の定石(フィンランド、香港、カナダを見よ)、②テスト競争では学力は身につかない(イングランド、アメリカを見よ)、③日本の結果をみると、公式など結論を指示された設問に応用することはできるが、身の回りの具体的な事柄に科学的思考を応用することはどちらかといえば苦手、④日本の子どもたちは「科学への興味・関心や科学の楽しさを感じている」生徒の割合は低く、「観察・実験などを重視した理科の授業を受けていると認識している」生徒の割合も低い。これは自ら意欲的に学んでいないことを示している、⑤日本の科学の学力格差は数学に比べると学校間格差が小さい、一方、フィアランドはほぼゼロである、⑥PISAが定義する学力は、日本人がこれまで考えてきた、知識の量や、技能の正確さ・スピードを測るものではなくそれらを活用するプロセスを測るものである、だから、結論を与える授業ではだめで、身の回りから問いを発し、原理・原則に戻って考えるというような議論の中から考える授業が求められている、と報告した。
池田さんは、フランスの国民教育省のコメントやル・モンド紙の特集から、これまで2回のPISA結果とは違うフランスのPISA2006に対する反応を紹介した。過去2回とはちがい、少しはPISA結果に動揺している様子がある。それは「前回のPISAの結果はドイツ、スイス、日本にショックを与えたが、今回はフランスの番かもしれない」とか「フランスでは、PISAはそれほど深刻には受け取られていなかったが、この2006年調査によって事態は変わる可能性はある」、といった反応があるからだ。また、ル・モンド紙が「15歳の生徒に科学を好きにさせることは可能である。すべての小学校で、好奇心旺盛なその時期に、自ら作業をするようなスタイルの授業の実施が必要である」といった教育の方法にまで言及している、という興味深い報告もなされた。
広瀬さんは、前回と同じように今回もマスコミが、日本のランクが落ちたことを強調しており、日本は「あおられる学力不安社会」になっているとし、事実の冷静な認識と分析のためには①15位以内に順位を得た国のなかで、人口1億を超える大きな国は日本のみである、②学力パフォーマンスを分析する上で、少なくとも学習指導要領といったカリキュラム政策要因のみならず、学校組織要因(教員定数、学級編制など)、家族的背景要因、社会経済的要因、大衆消費文化的要因が指標として設定されなければならない、③社会経済的状況(格差社会)自体が抜本的に是正されなければならない、ことを指摘。最後に、学力以外に、人権保障度、文化的アイデンティティ保障度が調査されないのはなぜか、PISA学力とグローバル経済におけるエリート育成の親和性について分析する必要があるのではないか、など基本的な問題点にも触れた。
これを受けたフロアーとの議論においては、PISAをどう評価し位置づけるのか、コンピテンシーとリテラシーの関係、今回のマスコミ報道の評価、ユネスコの学習論との異同などが論点となったが、時間の関係で詰めるまでにはいたらなかった。
最後に、桜井さんがPISAの枠内で議論するだけでなく、一歩外に出てみることが必要でないか、日本の子どもたちが「意欲」では最下位に近いにもかかわらず、「成績」では上位をとっているというギャップも子どもを痛める問題ではないのか、などとコメントした。