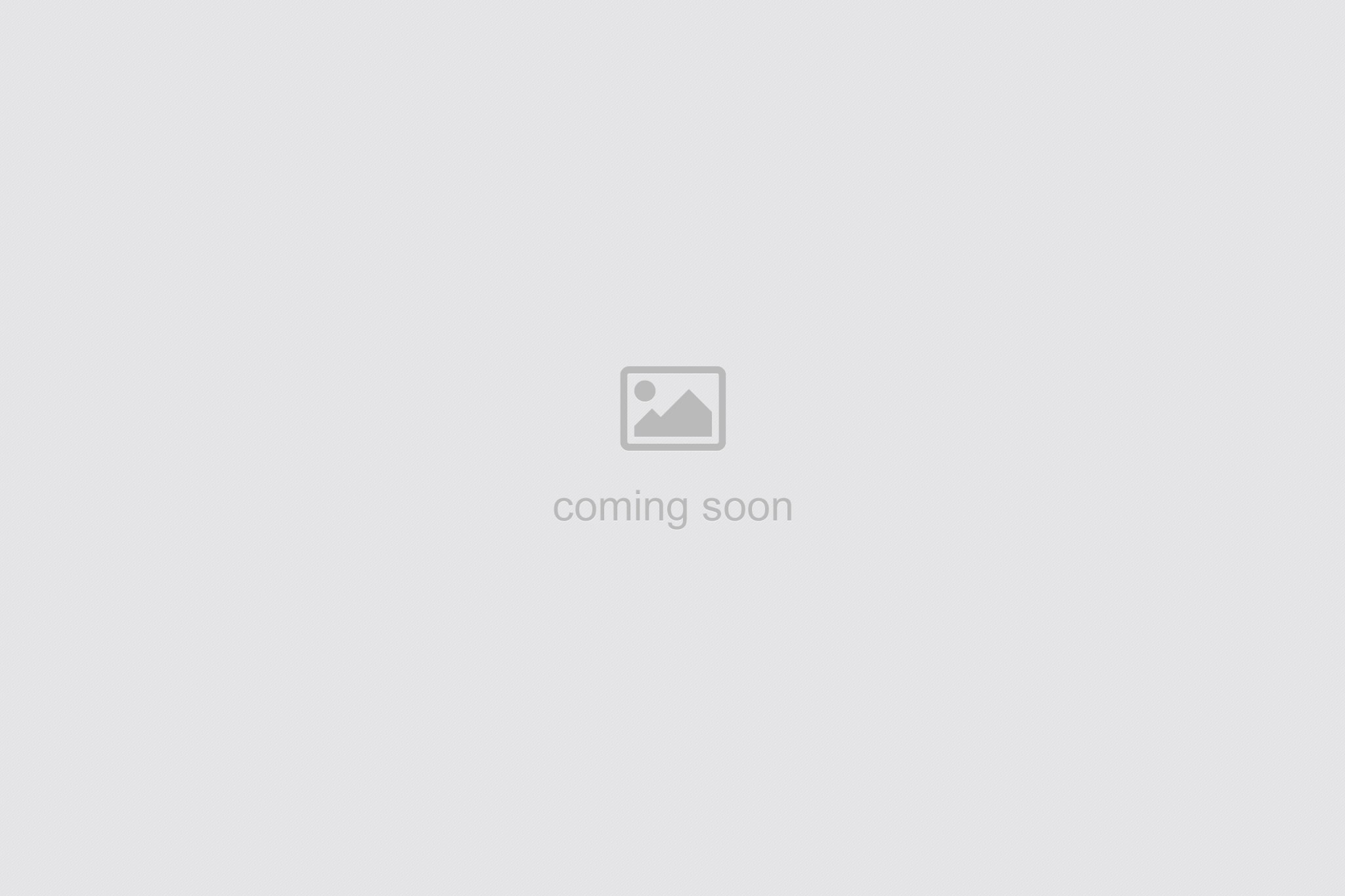活動報告:2010年
「生徒の学習到達度調査(PISA)2009」の結果公表について
2010-12-07
|
|
|
|
|
|
新しい観点から作り上げられたヨーロッパ仕様の国際学力調査PISAは、ようやくすべての問題が新規のものに取り替わり、今回で第2巡目に入った。ところが、世界にはテスト対策をとり始めた国があり、わが国もその一つである。テスト準備をする国の存在で、スキルを測定するTIMSS(国際数学・理科教育動向調査)とコンピテンシーを測定しようとするPISAの成績とが類似しつつあり(表1・2参照)、ランキングだけを見ればアジア諸国が上位を独占する勢いである。ヨーロッパが独自の学力観を確立して知のヨーロッパを構築しようとするPISAのもくろみが外れたと見るべきであろう。
国際的な動向では、国家間の格差は縮まる傾向にあるが、国内格差は拡大しつつあるとOECDは分析している。PISA2009の特徴は、成績上位層の増減によって国の順位や得点が大きく左右されている点である。このことは、かなりの国にテスト準備教育が普及してPISA型テストに強い子どもたちが生み出されていることをうかがわせる(表3参照)。
日本では、義務教育の成果が定着していない学力とみなされる成績下位層が少なくなり、このことは学校教育の成果と見なせるが、成績上位国に比べれば日本の「低学力」層の比率はまだ高く(表4参照)、さらに高校に進学していない者はこのデータから除外されていることを考えれば、いわゆる「底上げ」が日本にとって依然として大きな課題となっている。ちなみに、ヨーロッパ諸国では、教育制度の関係で義務教育期間にPISAを受験している。とりわけ、きめ細やかな指導で知られるフィンランドでは、今回この下位層が増えており、移民の増加などの原因が推測される。
ただし、教育労働者の国際組織である「教育インターナショナル(EI)」は、強制的な補習など性急な「底上げ」という方法をとることについては反対しており、「学習困難な成績不振児に対してより過酷な教育方法がとられる恐れがあり、また教員に対するプレッシャーが強まることを懸念する」と表明している。学力向上には、子どもたちを競争させたり劣等感を植え付けたり自信をなくすような方法を避け、長期的に取り組む課題である。
日本の推移を見ると、PISAとして新規に開発された「考える力」や「活用力」を測る問題によって一時的に学力低下したようにとらえられた(表5参照)。今回の調査では、読解力では改善が見られ、数学と科学についてはほぼ同じ成績となっている。現状を学力低下ととらえるかどうかよりも、今後日本が進むべき学力の質を問題にする必要がある。
今回詳細に分析された読解力については、日本においては、勉学環境として「趣味で読書することはない」という項目が44.2%とPISA2000に比べて10.8%も減少したが、OECD平均の37.4%までは減っていない。また、「読書は、大好きな趣味の一つだ」が42.0%、「本の内容について人と話をするのが好きだ」が43.6%、「本屋や図書館に行くのは楽しい」が66.5%と、OECD平均のそれぞれ33.4、38.6、43.1に比べて高率であるが、実態と合っているかどうか疑問である。読む本の種類として「コミック(マンガ)」は、72.4%となっておりPISA2000に比べて11.5%減少したものの、OECD平均は24.3%であることを考えると、きわめて高率である。コンピュータや携帯によって「Eメールを読む」と答えた日本の子どもたちはOECD平均よりも高率である反面、「ネット上でチャットをする」「ネット上で討論会またはフォーラムに参加する」と答えた者はきわめて少数であり、日本の子どもたちの言語コミュニケーションが特定の狭い人間関係のなかで行われていることをうかがわせる。
読解力について、日本でこの6年間にとられた対策は、フィンランド・メソッドやPISA型読解力指導というものであったが、形式的な問題解決学習や作文力養成を促すものになったり、量の拡大を図る画一的な読書活動の押しつけが目立っている。テスト準備教育よりは、一人ひとりの個人的な意志や生育歴に根ざしてことばの意味を深め、思考や想像力を広げ、創造力を培う教育を続けるべきである。このことについては、教育総研は詳しいレポートを作成中である。
これまで4回行われたPISA調査によって、学校の授業という狭い範囲の対応ではなく学力向上には社会的・経済的・文化的な背景が大きく作用していることなど、成績と学習条件の関連性はある程度見えてきたが、どのような状態の子どもにはどのような教育を準備すべきかについてはまだ確たる因果関係は見えていない。「考える力」や「学び続ける力」、「活用力」を強調する調査であるがゆえに、テスト対策をすれば成績が上がるというような対処は避けるべきであろう。
国際的な動向では、国家間の格差は縮まる傾向にあるが、国内格差は拡大しつつあるとOECDは分析している。PISA2009の特徴は、成績上位層の増減によって国の順位や得点が大きく左右されている点である。このことは、かなりの国にテスト準備教育が普及してPISA型テストに強い子どもたちが生み出されていることをうかがわせる(表3参照)。
日本では、義務教育の成果が定着していない学力とみなされる成績下位層が少なくなり、このことは学校教育の成果と見なせるが、成績上位国に比べれば日本の「低学力」層の比率はまだ高く(表4参照)、さらに高校に進学していない者はこのデータから除外されていることを考えれば、いわゆる「底上げ」が日本にとって依然として大きな課題となっている。ちなみに、ヨーロッパ諸国では、教育制度の関係で義務教育期間にPISAを受験している。とりわけ、きめ細やかな指導で知られるフィンランドでは、今回この下位層が増えており、移民の増加などの原因が推測される。
ただし、教育労働者の国際組織である「教育インターナショナル(EI)」は、強制的な補習など性急な「底上げ」という方法をとることについては反対しており、「学習困難な成績不振児に対してより過酷な教育方法がとられる恐れがあり、また教員に対するプレッシャーが強まることを懸念する」と表明している。学力向上には、子どもたちを競争させたり劣等感を植え付けたり自信をなくすような方法を避け、長期的に取り組む課題である。
日本の推移を見ると、PISAとして新規に開発された「考える力」や「活用力」を測る問題によって一時的に学力低下したようにとらえられた(表5参照)。今回の調査では、読解力では改善が見られ、数学と科学についてはほぼ同じ成績となっている。現状を学力低下ととらえるかどうかよりも、今後日本が進むべき学力の質を問題にする必要がある。
今回詳細に分析された読解力については、日本においては、勉学環境として「趣味で読書することはない」という項目が44.2%とPISA2000に比べて10.8%も減少したが、OECD平均の37.4%までは減っていない。また、「読書は、大好きな趣味の一つだ」が42.0%、「本の内容について人と話をするのが好きだ」が43.6%、「本屋や図書館に行くのは楽しい」が66.5%と、OECD平均のそれぞれ33.4、38.6、43.1に比べて高率であるが、実態と合っているかどうか疑問である。読む本の種類として「コミック(マンガ)」は、72.4%となっておりPISA2000に比べて11.5%減少したものの、OECD平均は24.3%であることを考えると、きわめて高率である。コンピュータや携帯によって「Eメールを読む」と答えた日本の子どもたちはOECD平均よりも高率である反面、「ネット上でチャットをする」「ネット上で討論会またはフォーラムに参加する」と答えた者はきわめて少数であり、日本の子どもたちの言語コミュニケーションが特定の狭い人間関係のなかで行われていることをうかがわせる。
読解力について、日本でこの6年間にとられた対策は、フィンランド・メソッドやPISA型読解力指導というものであったが、形式的な問題解決学習や作文力養成を促すものになったり、量の拡大を図る画一的な読書活動の押しつけが目立っている。テスト準備教育よりは、一人ひとりの個人的な意志や生育歴に根ざしてことばの意味を深め、思考や想像力を広げ、創造力を培う教育を続けるべきである。このことについては、教育総研は詳しいレポートを作成中である。
これまで4回行われたPISA調査によって、学校の授業という狭い範囲の対応ではなく学力向上には社会的・経済的・文化的な背景が大きく作用していることなど、成績と学習条件の関連性はある程度見えてきたが、どのような状態の子どもにはどのような教育を準備すべきかについてはまだ確たる因果関係は見えていない。「考える力」や「学び続ける力」、「活用力」を強調する調査であるがゆえに、テスト対策をすれば成績が上がるというような対処は避けるべきであろう。