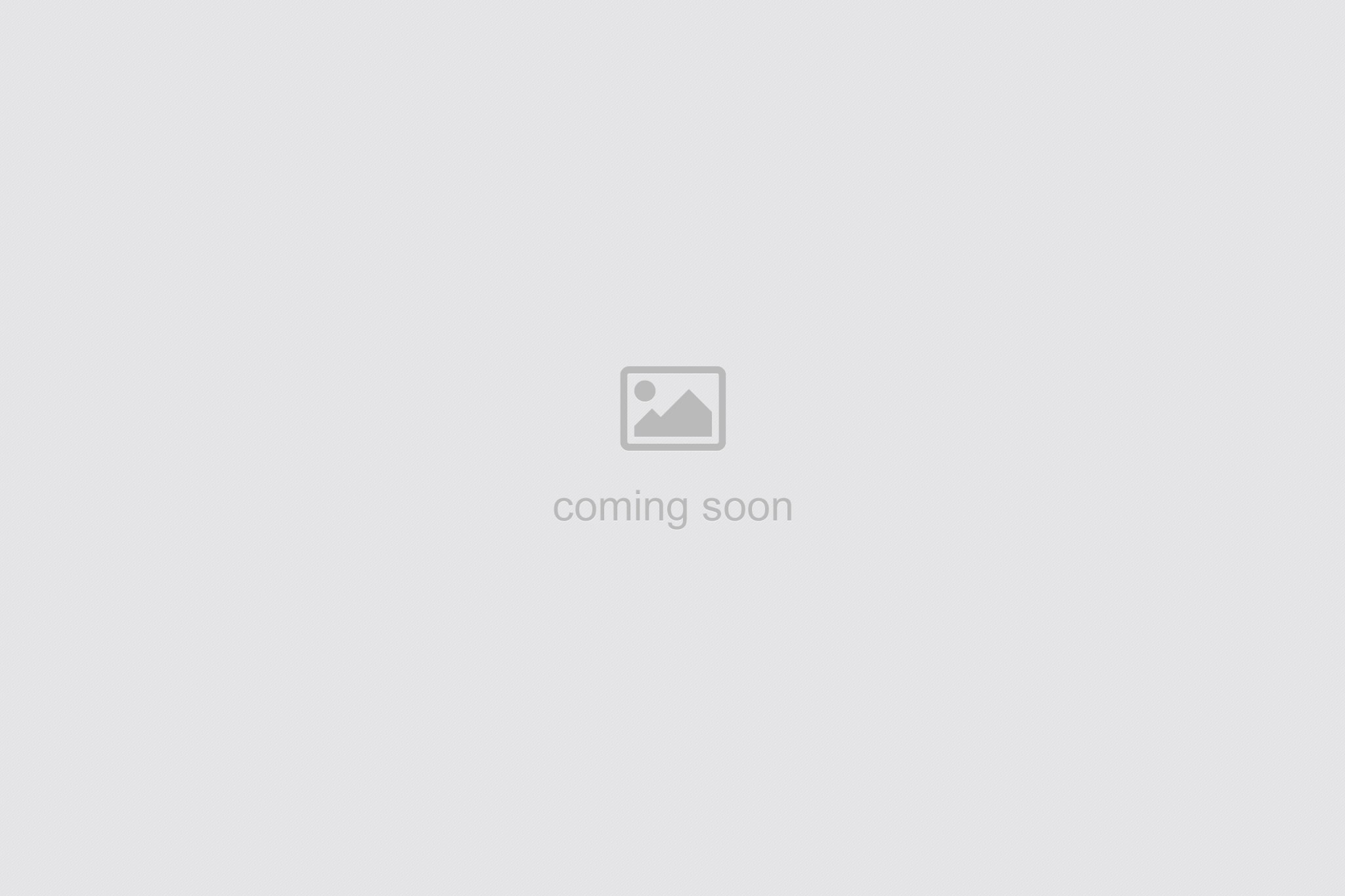活動報告:2011年
教育総研設立20周年記念集会
2011-10-25
国民教育文化総合研究所(1992年8月1日開所)の設立20周年記念集会が、さる7月29日に千葉県浦安市で開催された。記念集会は2部構成で、はじめにOECD事務総長教育政策特別顧問のアンドレア・シュライヒャーさんから、「PISAから見た21世紀の教育」と題してご講演をいただき、次に
シュライヒャーさんもパネリストの1人としてパネルディスカッションが、教育総研所長の嶺井正也さんをコーディネーターに、パネリストに福田誠治さん、筒井美紀さんを迎えて行われました。
Ⅰ、記念講演 「PISAから見た21世紀の教育」
(アンドレアス・シュライヒャ-さん)
シュライヒャーさんは今回の日本での滞在日程に東北地方への訪問を予定されていた。具体的には岩手県に入り、教育長と懇談する中でOECDとして中長期的に支援したいと述べています。 震災の実情などを聞くなかで、教員が命をかけて子どもたちを救おうとしたことに感動すると同時に、教員の仕事の線引きの難しさゆえに教員自身が疲れ果てている現実へのサポートの必要性を訴えました。
そして、この震災後においては、これまで言われてきた「生きる力」の育成という教育の目的も、その意味がちがったものとして具体的にあらわれてくるのではないかとも発言されました。
つまり、ひとりの市民として、社会の団結をいかに実現していくか、そのようなソーシャル・スキルが重要になってくるのではないか、と。
震災に関するお話の後、これまでのPISAの結果などを参照しながら、21世紀の学びのあり方について話をされました。
(なお、以下の文中の小見出しは、まとめる上で便宜上付けたものです。パネルディスカッションのまとめについても同様。)
1、求められる「学力」とは
まず前提として、学びは学校だけでなされるものではないということ、教員は知識を提供するのみではないということ、そして、子どもたち一人ひとりがそれぞれに才能をもつていることを前提として、多様な教授法が必要になるだろうということが確認されました。そして一人ひとりの能力を開花させる公平・公正な教育のあり方をどう描けばよいのかが、いま問われているのだということが述べられました。
では、いまどのような力が人間に求められているのか。
現実問題として、単純な手作業・知的作業は求められることが少なくなり、分析的作業や相互作用的な作業が求められている、つまり、関係をつくり協力していく力が求められているのであり、異なった文化にいかに対応していくかが問われているわけです。必要な情報等はある程度はインターネットで手に入れることができます。大切なことは、それらの中から何が重要かを見極める力なのです、とシュライヒャーさんは強調します。
急速に変化する世界の中で、さまざまな問題を自分との関連性において見極め、自律的に動いていく力が必要になっているのであり、そのための教育制度の改善は国内基準だけではなく、国際的な視点で成果をあげている例に学ぶ必要があると述べ、日本の場合、ともにPISAにおいて成果をあげている国であるけれども、韓国よりもフィンランドに学ぶものが多いのではないかと述べています。
このような学力観の転換に関して、シュライヒャーさんは数学の例を出して説明されました。
かつては、方程式や定理を覚えることが中心だったかもしれないが、いまは、それらの知識を現実の問題にどう適用するか、その問題の性質を数学の問題に置き換えて考えることができるかどうかが問われているのだ、と。「これは幾何の問題」、「これは代数の問題」といったように領域を区切るようなものではないのだ、と。結果として、計算のスピードが以前よりは遅くなったかもしれないけれど、それよりも知識の応用が大切なのです。既成の知識の再生ではなく、新たな状況にその知識をいかに応用できるか。
かつては一部の人が学べばよかったかもしれませんが、21世紀はすべての人が、上のような意味で学ばねばならないのであり、シュライヒャーさんはこれまで社会はずいぶんと人材を無駄にしてきたと指摘します。社会的な平等性の上に、ひとりひとりの能力をいかに開花させるか。その点でシュライヒャーさんは、韓国のやり方は、得点だけに着目すれば上位かもしれないけれども、エリートに資源を集中したために、社会的な不平等が増してきているとみています。
2、教員の質こそ大切
このような学力観に基づく教育政策が求められているわけですが、具体的にはどのような予算の使い方をするかという点が問われてきます。少なくともPISAの上位の国は、教員の質を重視し、専門職としてその労働条件の改善に力を入れているとのことです。
フィンランドでは、多くの学生が教員を志望している現実があり、シュライヒャーさんはこのように魅力ある仕事として教員が位置づいていることを高く評価し、同時に専門職として裁量権をもって学校主導で教育改革を遂行している点を紹介しています。教員の共同研究等の横のつながり(学校間のつながり)も重視しています。
一方で、日本で話題になることが多い一学級の人数(つまり少人数が望ましいとの見方)の関しては、子どもたちの能力開花という点で必須であるとの位置づけはしませんでした。それよりも、教員の質重視とのことでした。
3、日本の評価
日本ではPISAの得点ばかりが話題にされますが、シュライヒャーさんによれば、ここ10年ほどの間、日本のスコアにはほとんど変化はなく、むしろ、従来のような既成の知識の再生という能力ではなく、自由記述方式への回答にみられるように、知識を深いところで理解し、その応用の力に関して改善の度合いが高いと評価しています。読書に関しても、日本では、楽しみで本を読む子どもたちの率が上がってきているとのことです。
シュライヒャーさんは、PISAとは教育制度についての情報を共有できる強力なツールだといいます。求められるのは、継続的な学ぶ力を重視する、すべての子どもの成功を導く制度です。ここでは多様性はチャンスととらえられ、分けるのではなく統合された学びが追求されていくことになります。
Ⅱ、パネルディスカッション「PISAから見た21世紀の教育」
シュライヒャーさんのご講演を受けて、嶺井正也さんをコーディネーターに、そして、シュライヒャーさん、福田誠治さん(都留文科大学教員)、筒井美紀さん(法政大学教員)をパネリストとして、ご講演の内容を深めていきました。ここでは、どのような議論があったのかを、シュライヒャーさんの発言を中心にして簡単にまとめます。
なお、シュライヒャーさんの考え方については、教育総研編集の『教育と文化』第60号(2010年7月)に「21世紀の学びの実情」と題してご本人の原稿(日本語訳)が載せられていますので、ぜひご参照ください。
1、 OECDの社会像・人間像
まず、福田さんからは、PISAは「いままで何を学んだか」ではなく、「これから何ができるか」を測ろうとしているのだと指摘し、何のために学ぶのか、その哲学がいま問われているのではないか、また、筒井さんからは、PISAが測れていない能力とは何か、また、講演で述べられたような学力観の転換が大学入試と結びつかない限り、なかなか日本の学校現場では理解が得られないのではないかとの発言があり、
これに応えて、シュライヒャーさんから、はじめに、OECDのもつ社会像・人間像の説明がありました。次の3つが社会としての成功の要因になるとのことです。
① 生徒が社会文化的なツールを正しく操れるかどうか。
② 個人として自律的に行動できるかどうか。
③ 他者とともに生きることができるかどうか。
そして、講演でも述べられていたように、知識の蓄積自体の価値は下がってきていること、明らかになった知識を社会として集団的に共に使っていくことが大事になっていること、すべての人が社会に参加することの必要性が語られました。
2、なぜ測定するのか
また、PISAは何を測定しているのかという点に関しては、まず前提として、ごく小さな部分しかはかれていないこと、テストという形式も一つの手段にすぎないことの理解が重要であるとした上で、それでももっと多くのものが測れるのではないかと考えていること、テストという方法ではなく観察という方法も開発が必要であることなどが述べられました。
そもそも、なぜ「測る」ということが大切なのか。これについては、見えないものは改善できないから、との理由が述べられました。
ただし、「テスト文化」は変えていかなければならない課題であるとされています。アメリカやイギリスなどはテスト準備をしても、結果としてそれほど結果は伸びていないのであり、創造的に知を使うこと、テストと教科書との関係を断ち切ることも必要になるとのことでした。
3、PISAが測っているもの
テストといえば、日本では当然のように個人の能力が測られているのだと前提するけれども、シュライヒャーさんによれば、PISAの設計は、個人を測っているのではなく、統計上の問題として、教育制度の改善のために全体としての傾向を測っているのだと注意を述べました。
つまり、「個人には関心がない」というわけです。なぜなら、それぞれの子どもたちのことは教員がよく知っているのであり、PISAの必要はないからです。PISAは全体像を明らかにするためのものなのです。
PISAが示しているのはあくまでも平均像なわけですが、しかし、PISAの方法に関しては、個人の生活経験がテストの点数に反映されてしまうような設計になっている点、つまり、日本では、テスト内容が生活から遊離したものになることで客観性を担保することが発想されるが、PISAはそうではない、この点をどう考えればよいのか。
これに対しては、PISAはそのような意味での客観性はある程度犠牲にしているとのことでした。実生活での経験の積み方を問うているわけです。
4、障害児をどうとらえているか
PISAが集団的パフォーマンスを測定するということに関して、コーディネーターの嶺井さんからは、障害児の存在をどのように位置づけているかとの質問が出されました。
シュライヒャーさんは、そのことの分析はすでになされているとして、結論として、インクルージョンの方向性を示しました。つまり、たとえば、留年制度があれば、学業成功に対する社会的背景の影響力を大きくしてしまうと同じように、障害児を分離すれば、学びに対する障害の影響を大きくしてしまう、と。国により違いがあるとの注釈つきではあったが、インクルージョンのほうが、障害が学習の成功に与える影響は少ないとの分析が紹介された。なお、格差という点でいえば、日本は社会経済的影響が学校間格差として大きくなっているとの指摘があった。
5、PISAの今後
さて、議論が進む中でPISAの今後に話が及んだ。PISAは対人関係や個人内部のことは測れないとしながらも、 シュライヒャーさんは測定できないものは少ないとの考えを示し、2012年の調査の時には、子どもが問題と相互作用し、問題自体が変化していくようなダイナミックな問題解決のあり方を導入したいと述べ、また2015年には、集団をベースとして協力する力、社会的な力をみるような問題解決も考えていることが披露されました。
しかし、これにはPISA参加国の合意が必要であり、PISA自体のあり方も今後ますます進展していくだろうとのことでした。
6、社会の「成功」とは
このような集団としての力の測定は、かねてからPISAが目指していた方向性でしたが、そこで前提とされている変化した社会における個人像はいわば「強い個人」なのではないかとのコーディネーターからの問いかけに対して、 シュライヒャーさんはっきりと次のように反応していた。
つまり、社会の成功とは個人の成功の総和ではない、自分のために知識の蓄えても、他者と共有し、まわりに広げていかなければ意味がない、誰かが偉大な発明をするというよりも、知的リソースの活用が問題になっているのだ、と。
このように大きな視野からの「成功」のイメージだとすれば、筒井さんから指摘があったように、教育制度のみではなく福祉の問題や貧困の問題としてPISAが目指しているものをとらえ返す必要も出てくる。シュライヒャーさんは、不平等が次の世代につながらないような、貧困の影響を緩和するような制度の工夫が必要だと述べ、この点に関するフィンランドやカナダの例を評価していました。
7、教員の質に投資
ところで、教育の質は教員の質にかかっている、という点は講演でも強調されていましたが、ここでも教員の能力開発の機会が不可欠である点や理論と実践を結びつけることの大切さが指摘されました。学級の子どもの数に関しては、少人数が効果がないというのではないが、資金の使い方として、すべてを一度に改善していくことはできないので、よりよい結果を得るためにまずやるべきは、教員の質に投資するということでした。
おわりに -PISAの意義-
このパネルディスカッションを通して、会場に集まった多くの教職員に、PISAが何を問題とし、何を測っているのか・測ろうとしているのか、そしていま「学力」はどのように捉え直されようとしているのか、その基本的な部分がよく伝わったのではないでしょうか。
どうしても、測定結果にばかり気になってしまい、その数字自体が神格化され、絶対視され、その向上が「学力」の向上であるかのように思いこんでしまうのが、今の日本の状況でしょう。
最近ではよく「エビデンスが大事だ」といわれるけれども、筒井さんが指摘するように、それは統計を示すことで終わるものではなく、それを基にして議論をしていくことなのです。何かを単に継承しそれを再現してみせる能力の育成が教育に求められているのではなく、協調性を大切にしながら何かを生み出していく力が求められているのですから、数字を出して終わりなどということにはならないはずです。
また、福田さんが指摘するように、PISAは新しい学力観を提示したわけです。競争ではなく協力を基盤として、集団の力に着目するわけです。とくに、平等と質がつながることをデータで示したのがPISAだったのであり、競争すれば学力が上がるという考え方をひっくり返したわけです。
そして、嶺井さんの言うように、他者と知を共有する社会で求められるリテラシーが問題となっているのです。
シュライヒャーさんもパネリストの1人としてパネルディスカッションが、教育総研所長の嶺井正也さんをコーディネーターに、パネリストに福田誠治さん、筒井美紀さんを迎えて行われました。
Ⅰ、記念講演 「PISAから見た21世紀の教育」
(アンドレアス・シュライヒャ-さん)
シュライヒャーさんは今回の日本での滞在日程に東北地方への訪問を予定されていた。具体的には岩手県に入り、教育長と懇談する中でOECDとして中長期的に支援したいと述べています。 震災の実情などを聞くなかで、教員が命をかけて子どもたちを救おうとしたことに感動すると同時に、教員の仕事の線引きの難しさゆえに教員自身が疲れ果てている現実へのサポートの必要性を訴えました。
そして、この震災後においては、これまで言われてきた「生きる力」の育成という教育の目的も、その意味がちがったものとして具体的にあらわれてくるのではないかとも発言されました。
つまり、ひとりの市民として、社会の団結をいかに実現していくか、そのようなソーシャル・スキルが重要になってくるのではないか、と。
震災に関するお話の後、これまでのPISAの結果などを参照しながら、21世紀の学びのあり方について話をされました。
(なお、以下の文中の小見出しは、まとめる上で便宜上付けたものです。パネルディスカッションのまとめについても同様。)
1、求められる「学力」とは
まず前提として、学びは学校だけでなされるものではないということ、教員は知識を提供するのみではないということ、そして、子どもたち一人ひとりがそれぞれに才能をもつていることを前提として、多様な教授法が必要になるだろうということが確認されました。そして一人ひとりの能力を開花させる公平・公正な教育のあり方をどう描けばよいのかが、いま問われているのだということが述べられました。
では、いまどのような力が人間に求められているのか。
現実問題として、単純な手作業・知的作業は求められることが少なくなり、分析的作業や相互作用的な作業が求められている、つまり、関係をつくり協力していく力が求められているのであり、異なった文化にいかに対応していくかが問われているわけです。必要な情報等はある程度はインターネットで手に入れることができます。大切なことは、それらの中から何が重要かを見極める力なのです、とシュライヒャーさんは強調します。
急速に変化する世界の中で、さまざまな問題を自分との関連性において見極め、自律的に動いていく力が必要になっているのであり、そのための教育制度の改善は国内基準だけではなく、国際的な視点で成果をあげている例に学ぶ必要があると述べ、日本の場合、ともにPISAにおいて成果をあげている国であるけれども、韓国よりもフィンランドに学ぶものが多いのではないかと述べています。
このような学力観の転換に関して、シュライヒャーさんは数学の例を出して説明されました。
かつては、方程式や定理を覚えることが中心だったかもしれないが、いまは、それらの知識を現実の問題にどう適用するか、その問題の性質を数学の問題に置き換えて考えることができるかどうかが問われているのだ、と。「これは幾何の問題」、「これは代数の問題」といったように領域を区切るようなものではないのだ、と。結果として、計算のスピードが以前よりは遅くなったかもしれないけれど、それよりも知識の応用が大切なのです。既成の知識の再生ではなく、新たな状況にその知識をいかに応用できるか。
かつては一部の人が学べばよかったかもしれませんが、21世紀はすべての人が、上のような意味で学ばねばならないのであり、シュライヒャーさんはこれまで社会はずいぶんと人材を無駄にしてきたと指摘します。社会的な平等性の上に、ひとりひとりの能力をいかに開花させるか。その点でシュライヒャーさんは、韓国のやり方は、得点だけに着目すれば上位かもしれないけれども、エリートに資源を集中したために、社会的な不平等が増してきているとみています。
2、教員の質こそ大切
このような学力観に基づく教育政策が求められているわけですが、具体的にはどのような予算の使い方をするかという点が問われてきます。少なくともPISAの上位の国は、教員の質を重視し、専門職としてその労働条件の改善に力を入れているとのことです。
フィンランドでは、多くの学生が教員を志望している現実があり、シュライヒャーさんはこのように魅力ある仕事として教員が位置づいていることを高く評価し、同時に専門職として裁量権をもって学校主導で教育改革を遂行している点を紹介しています。教員の共同研究等の横のつながり(学校間のつながり)も重視しています。
一方で、日本で話題になることが多い一学級の人数(つまり少人数が望ましいとの見方)の関しては、子どもたちの能力開花という点で必須であるとの位置づけはしませんでした。それよりも、教員の質重視とのことでした。
3、日本の評価
日本ではPISAの得点ばかりが話題にされますが、シュライヒャーさんによれば、ここ10年ほどの間、日本のスコアにはほとんど変化はなく、むしろ、従来のような既成の知識の再生という能力ではなく、自由記述方式への回答にみられるように、知識を深いところで理解し、その応用の力に関して改善の度合いが高いと評価しています。読書に関しても、日本では、楽しみで本を読む子どもたちの率が上がってきているとのことです。
シュライヒャーさんは、PISAとは教育制度についての情報を共有できる強力なツールだといいます。求められるのは、継続的な学ぶ力を重視する、すべての子どもの成功を導く制度です。ここでは多様性はチャンスととらえられ、分けるのではなく統合された学びが追求されていくことになります。
Ⅱ、パネルディスカッション「PISAから見た21世紀の教育」
シュライヒャーさんのご講演を受けて、嶺井正也さんをコーディネーターに、そして、シュライヒャーさん、福田誠治さん(都留文科大学教員)、筒井美紀さん(法政大学教員)をパネリストとして、ご講演の内容を深めていきました。ここでは、どのような議論があったのかを、シュライヒャーさんの発言を中心にして簡単にまとめます。
なお、シュライヒャーさんの考え方については、教育総研編集の『教育と文化』第60号(2010年7月)に「21世紀の学びの実情」と題してご本人の原稿(日本語訳)が載せられていますので、ぜひご参照ください。
1、 OECDの社会像・人間像
まず、福田さんからは、PISAは「いままで何を学んだか」ではなく、「これから何ができるか」を測ろうとしているのだと指摘し、何のために学ぶのか、その哲学がいま問われているのではないか、また、筒井さんからは、PISAが測れていない能力とは何か、また、講演で述べられたような学力観の転換が大学入試と結びつかない限り、なかなか日本の学校現場では理解が得られないのではないかとの発言があり、
これに応えて、シュライヒャーさんから、はじめに、OECDのもつ社会像・人間像の説明がありました。次の3つが社会としての成功の要因になるとのことです。
① 生徒が社会文化的なツールを正しく操れるかどうか。
② 個人として自律的に行動できるかどうか。
③ 他者とともに生きることができるかどうか。
そして、講演でも述べられていたように、知識の蓄積自体の価値は下がってきていること、明らかになった知識を社会として集団的に共に使っていくことが大事になっていること、すべての人が社会に参加することの必要性が語られました。
2、なぜ測定するのか
また、PISAは何を測定しているのかという点に関しては、まず前提として、ごく小さな部分しかはかれていないこと、テストという形式も一つの手段にすぎないことの理解が重要であるとした上で、それでももっと多くのものが測れるのではないかと考えていること、テストという方法ではなく観察という方法も開発が必要であることなどが述べられました。
そもそも、なぜ「測る」ということが大切なのか。これについては、見えないものは改善できないから、との理由が述べられました。
ただし、「テスト文化」は変えていかなければならない課題であるとされています。アメリカやイギリスなどはテスト準備をしても、結果としてそれほど結果は伸びていないのであり、創造的に知を使うこと、テストと教科書との関係を断ち切ることも必要になるとのことでした。
3、PISAが測っているもの
テストといえば、日本では当然のように個人の能力が測られているのだと前提するけれども、シュライヒャーさんによれば、PISAの設計は、個人を測っているのではなく、統計上の問題として、教育制度の改善のために全体としての傾向を測っているのだと注意を述べました。
つまり、「個人には関心がない」というわけです。なぜなら、それぞれの子どもたちのことは教員がよく知っているのであり、PISAの必要はないからです。PISAは全体像を明らかにするためのものなのです。
PISAが示しているのはあくまでも平均像なわけですが、しかし、PISAの方法に関しては、個人の生活経験がテストの点数に反映されてしまうような設計になっている点、つまり、日本では、テスト内容が生活から遊離したものになることで客観性を担保することが発想されるが、PISAはそうではない、この点をどう考えればよいのか。
これに対しては、PISAはそのような意味での客観性はある程度犠牲にしているとのことでした。実生活での経験の積み方を問うているわけです。
4、障害児をどうとらえているか
PISAが集団的パフォーマンスを測定するということに関して、コーディネーターの嶺井さんからは、障害児の存在をどのように位置づけているかとの質問が出されました。
シュライヒャーさんは、そのことの分析はすでになされているとして、結論として、インクルージョンの方向性を示しました。つまり、たとえば、留年制度があれば、学業成功に対する社会的背景の影響力を大きくしてしまうと同じように、障害児を分離すれば、学びに対する障害の影響を大きくしてしまう、と。国により違いがあるとの注釈つきではあったが、インクルージョンのほうが、障害が学習の成功に与える影響は少ないとの分析が紹介された。なお、格差という点でいえば、日本は社会経済的影響が学校間格差として大きくなっているとの指摘があった。
5、PISAの今後
さて、議論が進む中でPISAの今後に話が及んだ。PISAは対人関係や個人内部のことは測れないとしながらも、 シュライヒャーさんは測定できないものは少ないとの考えを示し、2012年の調査の時には、子どもが問題と相互作用し、問題自体が変化していくようなダイナミックな問題解決のあり方を導入したいと述べ、また2015年には、集団をベースとして協力する力、社会的な力をみるような問題解決も考えていることが披露されました。
しかし、これにはPISA参加国の合意が必要であり、PISA自体のあり方も今後ますます進展していくだろうとのことでした。
6、社会の「成功」とは
このような集団としての力の測定は、かねてからPISAが目指していた方向性でしたが、そこで前提とされている変化した社会における個人像はいわば「強い個人」なのではないかとのコーディネーターからの問いかけに対して、 シュライヒャーさんはっきりと次のように反応していた。
つまり、社会の成功とは個人の成功の総和ではない、自分のために知識の蓄えても、他者と共有し、まわりに広げていかなければ意味がない、誰かが偉大な発明をするというよりも、知的リソースの活用が問題になっているのだ、と。
このように大きな視野からの「成功」のイメージだとすれば、筒井さんから指摘があったように、教育制度のみではなく福祉の問題や貧困の問題としてPISAが目指しているものをとらえ返す必要も出てくる。シュライヒャーさんは、不平等が次の世代につながらないような、貧困の影響を緩和するような制度の工夫が必要だと述べ、この点に関するフィンランドやカナダの例を評価していました。
7、教員の質に投資
ところで、教育の質は教員の質にかかっている、という点は講演でも強調されていましたが、ここでも教員の能力開発の機会が不可欠である点や理論と実践を結びつけることの大切さが指摘されました。学級の子どもの数に関しては、少人数が効果がないというのではないが、資金の使い方として、すべてを一度に改善していくことはできないので、よりよい結果を得るためにまずやるべきは、教員の質に投資するということでした。
おわりに -PISAの意義-
このパネルディスカッションを通して、会場に集まった多くの教職員に、PISAが何を問題とし、何を測っているのか・測ろうとしているのか、そしていま「学力」はどのように捉え直されようとしているのか、その基本的な部分がよく伝わったのではないでしょうか。
どうしても、測定結果にばかり気になってしまい、その数字自体が神格化され、絶対視され、その向上が「学力」の向上であるかのように思いこんでしまうのが、今の日本の状況でしょう。
最近ではよく「エビデンスが大事だ」といわれるけれども、筒井さんが指摘するように、それは統計を示すことで終わるものではなく、それを基にして議論をしていくことなのです。何かを単に継承しそれを再現してみせる能力の育成が教育に求められているのではなく、協調性を大切にしながら何かを生み出していく力が求められているのですから、数字を出して終わりなどということにはならないはずです。
また、福田さんが指摘するように、PISAは新しい学力観を提示したわけです。競争ではなく協力を基盤として、集団の力に着目するわけです。とくに、平等と質がつながることをデータで示したのがPISAだったのであり、競争すれば学力が上がるという考え方をひっくり返したわけです。
そして、嶺井さんの言うように、他者と知を共有する社会で求められるリテラシーが問題となっているのです。